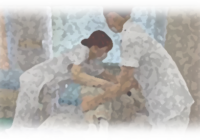2月12日から25日にかけて、東乗鞍古墳(天理市乙木町・杣之内町)において、8回目となる発掘調査を、天理大学歴史文化学科と天理市教育委員会が共同で行いました。桑原久男教授、小田木治太郎教授、橋本英将教授の指導のもと、同学科の学生27名、奈良女子大学の学生2名を加えた総勢29名の学生が参加しました。
天理大学と天理市は、2014年に包括的連携を締結。この協定に基づき、2017年、本学文学部と天理市教育委員会が「天理市内埋蔵文化財の調査・研究に関する覚書」を交わし、2018年から共同調査として、天理市内における古墳等の発掘調査や物理探査を行うこととなりました。
調査対象である東乗鞍古墳は、6世紀前半に築造された古墳時代後期の前方後円墳で、後円部には横穴式石室が南に開口しています。石室内には石棺が2基あり、奥の棺は、阿蘇溶結凝灰岩製(あそようけつぎょうかいがんせい)の刳抜式家形石棺(くりぬきしきいえがたせっかん)です。手前の棺は、組合式石棺(くみあわせしきせっかん)で、二上山産の底石が残る貴重な遺跡です。
これまでの調査で、全長が約83メートルに及ぶこと、また、前方部・後円部に周濠があることが分かっています。
今年は、後円部・くびれ部南側の墳丘隣接地に2箇所の調査区を設けました。調査区の一つは、昨年も一部発掘した「第12トレンチ拡張区」で、前方後円墳の「くびれ部」の一番下の部分を確認することを目的としました。今回の調査では「くびれ部」を確認するまでには至りませんでしたが、2月17日、周濠と堤の一部を確認するこができました。
もう一つの調査区「第13トレンチ」では、「後円部」南側において、円の裾部分、周濠、外堤を捉えることを目的としました。裾の部分は見つかりませんでしたが、周濠は確認することができ、外堤もほぼ確定することができました。
また、ここは石室開口部から延長方向上にあたる箇所で、周濠の底からは土師器や須恵器などの遺物が、例年よりも非常に多く発掘されました。
調査期間の終盤は、この冬一番の寒さとなる天候となり雪の降る日もありましたが、学生と教員が力を合わせて地道に発掘を続け、今年も発掘調査の成果を得ることができました。




歴史文化学科 考古学・民俗学研究コース 橋本英将教授コメント
寒空の下での作業は体力を要するものでしたが、学生たちのチームワークがよく、元気にとてもいい雰囲気で実習に取り組んでくれました。この発掘調査は、天理市教育委員会や、旭日大教会様をはじめとする地権者の方々、周辺の自治会の皆様など、様々な方々のご協力のもと実施できていること、そして、とても貴重な機会であることを、日頃、学生たちに伝えています。発掘現場へ向かう道中で地元の方と会った時や、関係者の方が現場へ来られた時には、学生たちが積極的に挨拶する様子が見られました。実習をとおして、学生たちは、発掘だけでなく地域連携の大切さも学んでくれたのではないかと思っています。
実習に参加した具志一諒さん(考古学・民俗学2年・四條畷学園)コメント
今回、初めて参加しました。実習の始めは土を掘る作業が続いて、しんどいと思っていました。でも、毎日作業を進めるうちに、地層が見えてきたり遺物が見つかってきたりして、しんどさ以上の楽しさが感じられるようになりました。授業でこの実習について話を聴いている時から、興味があってとても楽しみにしていました。体全体を動かして得る学びはすごく身につくと思いますし、五感で得る学びはとても貴重だと思いました。