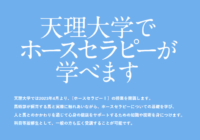天理大学英米語学科は、1月17日、「プレゼンテーション動画発表会」を杣之内キャンパス4号棟にて開催いたしました。
これは、英米語専攻3年次生の必修科目「英語F (Presentation) 」の秋学期最終の授業で行われたものです。
「英語F (Presentation) 」では、1年次生から続けてきた英語でのプレゼンテーション・スキル習得の仕上げとして、「天理大学」と「天理市」の魅力を英語で伝えるPR動画を制作するという課題に取り組みました。
小松﨑利明 英米語学科准教授指導のもと、学生たちは、まず「自分たちで自分たちの学びをデザインし実践する」という目的で、学生同士で相談して授業シラバスを作りました。
シラバスには、授業の到達目標と概要、それらを修得するための全15回の授業計画を記載しました。また、「成績評価方法・評価基準」も学生たち自身が話し合って設定しました。
次に、履修者12名は、「天理市紹介動画」と「天理大学英米語学科紹介動画」の2グループに分かれて、PR内容の情報収集をはじめ、撮影場所の選定や動画の台本作成など、動画制作の準備を行いました。

10月25日の授業「第1回途中経過発表」では、各グループが作成案を動画やパワーポイントなどを使って説明し、参加した本学の大学職員や担当の小松﨑准教授が、それぞれのグループに改善点を伝えました。
学生たちは、それらのアドバイスを基に、グループで撮影内容や動画の見せ方、テロップの表示方法、BGM、英語表現などについて相談を重ねました。
その後、11月29日と12月20日にも「途中経過発表」を開催。教職員のアドバイスを受けた学生たちは、よりよいプレゼンテーションとなるよう、何度も再撮影・再編集を行い、動画の更なるブラッシュアップに取り組みました。

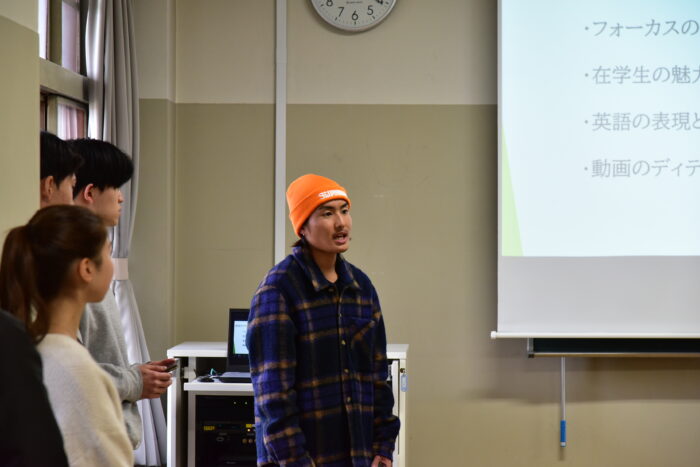
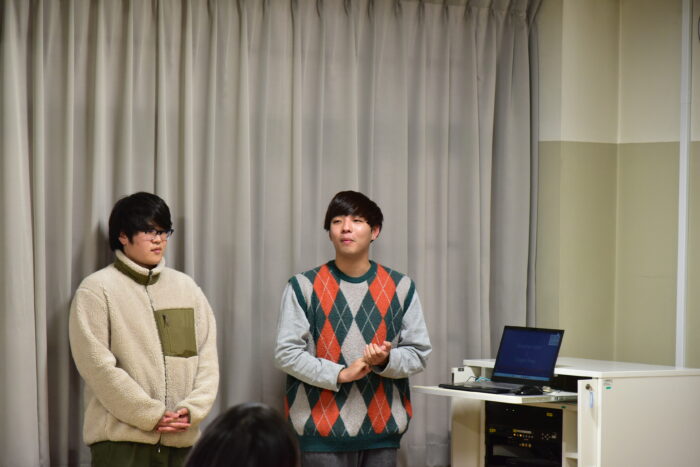

1月17日、「英語F (Presentation)」授業の最終日には、国際学部の教員をはじめ、人文学部の教員、様々な部署の職員が審査員として参加し、「プレゼンテーション動画発表会」が行われました。
発表会では、まず「天理市紹介動画」チームが秋学期の成果発表として、完成したPR動画を披露しました。
次に、「天理大学英米語学科紹介動画」チームが完成した動画を披露しました。
2つの動画視聴後には、審査員となった教職員から講評が述べられました。審査員からは、「天理大学」や「天理市」の魅力を伝えようと、創意工夫を凝らした点が高く評価されるとともに、積極的に授業に取り組んできた学生たちを労う言葉がかけられました。
また講評では、課題点も指摘されましたが、動画の今後の活用について、職員から提案がなされ、学生たちの授業成果が、PR動画として実用に至ることとなりました。


英米語学科では、学生たちが英語で発表することができる実践的なプレゼンテーション能力を養成していくため、今後も教職員や地域とも連携してこうした新たな学びの授業運営に積極的に取り組んでいく予定です。
参加学生のコメント
笠飯久代さん(外国語学科英米語専攻3年・天理教校学園)
天理大学は留学サポートや交換留学先の大学が充実していて、以前から、このたくさんの魅力を高校生に伝えたいと思っていました。「天理大学英米語学科紹介動画」の制作では、自分の伝えたい魅力だけでなく、グループの友達やほかの専攻の友達にもインタビューしていろんな魅力を動画に取り込みました。でも、魅力をただ詰め込むだけでは見ている高校生たちきちんと伝わらないので、経過報告でいただいた意見も参考にしながら、伝えたい内容を取捨選択しました。学生が中心となって進める授業は初めてで、こんなに悩んで考えた授業というのも初めてのことでしたが、グループで一つのことをやり遂げる達成感も味わえてとてもよかったと思います。
尾崎舜さん(外国語学科英米語専攻3年・天理)
動画のテーマが「天理市紹介動画」に決まってから、天理市の魅力スポットをメンバー6人で出し合いました。たくさんの意見が出ましたが、視聴対象を外国人観光客として定めたので、どのスポットであれば外国人観光客に天理市を訪れてみたいと思ってもらえるか、またどんな情報を求めているかを意識しながら、紹介する場所や食べ物を選定しました。撮影は6人それぞれが一つ以上のスポットを担当したので、それらの動画を編集する作業は大変でしたが、普段の授業だけでは生まれないようなやり取りや、友達の新しい一面も見ることができましたし、何よりも大学へ入ってから勉強してきた英語を活かす場ができてとても嬉しかったです。
担当教員コメント
小松﨑利明 英米語学科准教授
この授業は、どうすれば聞き手にわかりやすく説得力のある発信を行うことができるのかを、学生自らが模索し、見つけ出していくことを目指しました。それを英語を用いて行うわけですが、そこでは「英語〈を〉学ぶ」のではなく「英語〈で〉学ぶ」という姿勢が求められます。当初は慣れない学びの形に戸惑った学生もいましたが、グループ内で試行錯誤を重ね、また職員さんの力も借りながら、最後にはその努力を一つの形に結実させてくれました。私にとっては、一人一人の学生が持つ潜在的な力の大きさを感じさせられた1学期間でした。