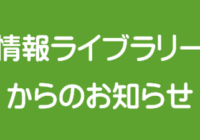2025年4月に天理大学人文学部国文学国語学科へご入学予定のみなさん、読書をしていますか。
言語脳科学・脳計測科学の研究者である東京大学大学院総合文化研究家の酒井邦嘉教授は「読書は脳の想像力を高める―なぜ「紙の本」が必要なのか―」(「生活協同組合研究」2018.5)のなかで、読書と脳の関係、読書で得られる効果を次のように説明しています。(以下、本文より抜粋)
***
「読む」という行為は、単に視覚的にそれを脳に入力するというのではなく、足りない情報を想像力で補い、曖昧なところを解決しながら「自分の言葉」に置き換えていくプロセスである。それは人間だけに与えられた、脳の驚くべき能力に支えられている。(略)人間の脳には、文や節の「構造」を見抜く能力が備わっている。文章を読むときも、文字だけでは足りない情報を想像力で補いつつ、そうした目に見えない文の構造をリアルタイムで頭の中で作りながら読んでいることになる。これが「自分の言葉に置き換えていく」と前に述べた意味なのである。(略)
思考力には、言語力と想像力の両方が必要である。そして思考力は知性、言語力は理性、想像力は感性と置き換えてもよい。つまり、知性は理性と感性の両方が必要である。理性が乏しければ情に流されるし、感性が少なければ論理の隙間を補うことができない。
人間の思考は言語を基礎として作られるが、言葉の力に想像力が付け加わることで、その着想が千変万化しうるのである。言語力と想像力を両輪とすることで、さらなる思考の飛躍や展開が可能となり、新たなアイディアを生むことにつながる。突き詰めて考えれば、人間の独創性の基礎には言語能力があることになる。
そして、生涯にわたる読書や学習の蓄積こそが、実際に「脳を創る」ことにつながる。
***
酒井教授が指摘する思考力=知性、言語力=理性、想像力=感性を身につけることが、大学で学ぶうえで、さらには社会人として生きていくうえで、みなさんの「強み」となります。さらに、大学ではその身につけた思考力・言語力・想像力をどのように活用するのか、その「方法」のいくつかを学ぶことになります。「方法」を効果的に学ぶためにも下地となる思考力・言語力・想像力を養っておくことが重要なのはいうまでもありません。
こうしたことから、国文学国語学科の専攻科目にかかわる図書をできるだけ多く読んで、4月からのあたらしい大学での学びにむけて準備をしてください。以下に学科教員がおすすめする新書をリストアップしました。いずれも公共の図書館で借りることができる、または書店やネットショップにて1,000円前後で入手できる書籍です。これから4月までのあいだにどれだけたくさんの本を読めるか、是非、チャレンジしてみてください。(国文学国語学科 西野由紀)
【国文学分野】
近藤信義『音感万葉集』(はなわ新書)
高木和子『源氏物語入門』(岩波ジュニア新書)
渡部泰明『和歌とは何か』 (岩波新書)
鈴木健一『知ってる古文の知らない魅力』(講談社現代新書)
小林ふみ子『へんちくりん江戸挿絵本』 (インターナショナル新書)
磯辺勝『文学に描かれた「橋」―詩歌・小説・絵画を読む』 (平凡社新書)
堀啓子『日本近代文学入門 12人の文豪と名作の真実』(中公新書)
【国語学分野】
阿辻哲次『日本人のための漢字入門』(講談社現代新書)
上野誠『入門 万葉集』(ちくまプリマー新書)
佐藤亮一『日本の方言』(角川ソフィア文庫)
井上史雄『日本語ウォッチング』(岩波新書)