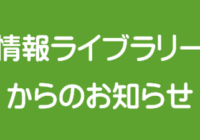《公開講座記録》【「大和学」への招待―橿原市の歴史と文化―】第2回
●2024年10月19日(土) 午後2:30
●テーマ:織豊政権と今井
●講師 天野 忠幸 (歴史文化学科 教授)
内容
橿原市の今井町は、戦国・織豊期に浄土真宗称念寺の寺内町として成立し、平成5年(1993)に文化財保護法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されると、平成29年(2017)には日本遺産「1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」~竹内街道・横大路~」を構成する文化財として認定された。そうした今井の成立過程を見ていく。
寺内町となる前の今井には、興福寺一乗院の荘園である今井荘が設けられた。しかし、経済機能としては、横大路(長谷街道)と下ツ道の交点にあたる八木が卓越していた。八木には市が立ち、土蔵や座が置かれ、有力領主である十市氏の保護を受ける。また、十市氏に並ぶ領主の越智氏も今井や八木への進出を図っていた。
戦国時代になると、本願寺と今井周辺の道場を取り次ぐ今井浄欽が現れる。しかし、1530年代に摂津・河内・大和を中心に起こった一向一揆が、今井を焼き払うことから、まだ浄土真宗の基盤は弱かったようだ。ところが、1550年代になると、本願寺教団の要人が吉野の飯貝本善寺に向かう際、今井または「今井兵部」の屋敷に宿泊する事例が頻出する。一向一揆が収束し、本願寺と室町幕府や大名たちとの和睦が成立すると、両者は一揆で荒廃した地域の復興のために協力して、寺内町を建設し経済発展を追い求める。今井もそうした情勢を受けて、発展し始めたのであろう。
1560年代に松永久秀が大和を支配するようになると、抗争に敗れた十市遠勝とその家族が今井で隠居することになった。これは、今井がアジール(避難所、聖域)としての性格を持っていたことを意味する。同様の性格を持つ都市として、堺や大坂、尼崎が挙げられる。この頃、十市氏家臣の河合氏も今井に住むようになり、江戸時代に今西に改姓している。片岡氏家臣の上田氏も1570年頃に移り住むようになった。この頃には「ツルヤ」や「なへや」といった今井在住の商人が見え始め、年貢米などの管理や換金を行っていることがわかる。今井の経済機能は八木を凌駕し、米の為替を取り扱う集散地としての役割を果たすようになっていた。
今井がこのような中立地帯としての立場を捨てたのが、三好三人衆・本願寺顕如方と織田信長方が戦った大坂本願寺合戦(1570~1580)の時期である。当時、三好三人衆は今井道場を取り立てるため興福寺と交渉するなど、本願寺側に立った政策を採っていたため、本願寺も三好三人衆に味方して、信長との戦いに踏み切ったのである。今井も大坂本願寺と共に戦ったが、天正3年(1575)に和睦すると、信長も「今井郷惣中」を赦免し、織田軍の狼藉を禁ずる朱印状を発給した。天正8年(1580)には信長が本願寺と勅命による講和を結び、本願寺を大坂から退去させ、畿内の平定を成し遂げた。そして、大和には検地と破城を指示する。翌年に明智光秀が信長の命令に従って、今井も破城を実行したことを確認しているので、今井が武士の城郭並みの土塁や堀を誇っていたことを示している。
信長の死後、羽柴秀吉が本願寺と蜜月関係を築き台頭する中で、近江浅井氏の家臣であった河瀬氏が「今井兵部」の名跡を継ぎ、復興に尽くした。新たな今井氏は豊臣政権の実務官僚としても重用され、道場は慶長5年(1600)に本願寺より親鸞聖人縁起を下付されて「称念寺」の寺号が許された。また、秀吉の弟秀長が大和・紀伊・和泉を拝領すると、郡山城下町の興隆のため堺や奈良、今井より住民を移住させた。今井氏は秀長段階の奈良でも活動していた痕跡がうかがえる。今井寺内町の経済力は、豊臣期に長足の発展を遂げたと言えよう。