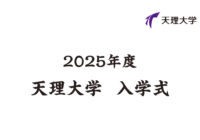天理大学の国際ボランティア・国際支援の実践的取り組みである「第21回 国際参加プロジェクト」が、2025年2月12日から26日にかけて、タイ王国にて実施されました。
今回は、天理大学人文部と国際学部の1年生から4年生の12名が参加し、マハーサーラカーム、バンコク、パヤオの3つの都市で、様々な活動を実施しました。
まず、学生たちは、本学の協定校 マハーサーラカーム大学のあるタイ東北部の町マハーサーラカームを訪問。この町の幼稚園・小学校・中学校・高校の児童や生徒を対象に、日本語と日本文化を通して、教育支援活動と交流活動を行いました。
学生たちは、子どもたちに身体を動かしながら楽しく日本語を学んでほしいと、「だるまさんが転んだ」をアレンジした「だるまさんの一日」、トランプゲーム、日本のお正月の伝統的な遊び「福笑い」といったゲームを用意しました。また、学生同士でそれぞれのゲームに工夫を凝らしたほか、ゲームで使うセリフを事前にタイ語で暗記しておくなど、できる限りの努力をして活動に取り組みました。


教育支援活動と交流活動後には、子どもたちと学生とで記念品制作を行いました。記念品には、生活の道具として日本人になじみの深い「うちわ」を選びました。無地の「うちわ」に桜や富士山、花火といった日本独特の絵をほどこし、それに子どもたちが思い思いにちぎった折り紙を張り付けました。
タイの教育機関での活動は、学生たちの積極的なはたらきかけによって、子どもたちが元気な大きな声で日本語を練習したり、ゲームを通した交流では歓声が沸き起こるなど、実りのある交流活動となりました。



マハーサーラカームでの活動後、学生たちはタイの首都バンコクへ移動しました。JICAバンコク事務所での研修のほか、天理教タイ出張所を訪問し、本学卒業生との交流機会を得ました。
また、教育の機会に恵まれていない子どもたちへの教育支援を行っている「シーカー・アジア財団」も訪問。財団運営の図書館でスラム街の歴史や現状に関する講演を受講し、その後、スラム街を見学しました。
財団は、タイ北部で暮らす少数民族「モン族」へも教育支援活動を行っており、山奥で高校に通えない彼らのために、学生寮を建設して子どもたちの通学を支援しています。本学学生たちは、この学生寮でホームステイを行い、自給自足の生活を送る「モン族」と一緒に寝泊まりし、日本と異なる生活を実体験することで、文化の違いについて各自がいろいろと考える機会となりました。


また、学生たちは、国際参加プロジェクト出発前の1月26日、スラム街の子どもたちとモン族の子どもたちの教育支援のために、天理駅にて募金活動を行い、集まった募金7万円を、2月20日、シーカー・アジア財団の現地日本人スタッフ 山田大貴さんにお渡ししました。
関本克良教授コメント
タイ人学生との共同ボランティアや、スラム街での活動、少数民族のモン族の村でホームスティなど、世界の現状を体験的に学ぶ貴重な内容になっています。体験を通して、「知る」ことよりも「感じる」ことの大切さを知ってもらいたいです。人生の早い時期に、世界の現状を肌で感じるような体験を、ぜひ経験してもらいたいと思います。