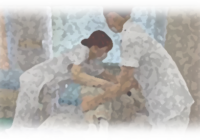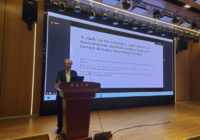作家の三浦しをんさんが、2月13日、天理大学を訪れ、天理大学附属の天理図書館と天理属参考館を見学しました。
2000年に長編小説『格闘する者に○』(草思社)で小説家としてデビューした三浦さんは、2006年、『まほろ駅前多田便利軒』(文藝春秋)で第135回直木賞を受賞(当時、20代での受賞は史上4人目)。2012年に『舟を編む』(光文社)で第9回本屋大賞、2015年に『あの家に暮らす四人の女』(中央公論新社)で第32回織田作之助賞、2018年には『ののはな通信』(KADOKAWA)で第25回島清恋愛文学賞を、それぞれ受賞しました。現在、直木賞の選考委員も務めています。
また、三浦さんはエッセイも執筆しており、日常生活や旅先での出来事などが等身大のユーモア溢れる筆致で綴られています。
三浦さんは、株式会社淡交社が発行する月刊「なごみ」で連載中のルポエッセイ「二度目の修学旅行」の取材のため天理市を訪れました。三浦さんは、かねてより貴重書やユニークな収蔵品が多数ある天理大学附属の天理図書館と天理参考館に興味を持っていたことから、「二度目の修学旅行」で取り上げるスポットとして両館を見学しました。
三浦さんは、天理大学附属天理図書館を訪れ、同館の三濱靖和副館長と森山恭二事務長の案内のもと、1階の正面カウンターをはじめ閲覧室や開架書庫、2階の展示室や講堂を見学しました。展示室では、一つひとつの作品をじっくりと見ながら、疑問に思うことを様々な角度から質問し取材を行いました。


図書館を後にした三浦さんは、続いて天理大学附属天理参考館を見学しました。ここでは、巽善信副館長が案内役を務め、1階・2階の「世界の生活文化」、3階の「世界の考古美術」、そして、現在開催中の企画展「墳墓のインテリアデザイン―墳墓観の変遷 漢から唐へ―」を見学しました。日本だけでなく世界各地の展示資料について、巽副館長が丁寧に説明を行いました。
天理大学創設者である中山正善・天理教2代真柱が、天理図書館と天理参考館を開設した思いや、様々な苦労のなか多数の書物や資料を収集したいきさつ、そして、それらを展示することの意義などについて、両館の担当者から説明を受けた三浦さんは、当時、まだ20代であった中山正善氏の先見の明に感服した様子でした。

その後、西浦忠一 天理大学理事長や本学 宗教主事の井上護夫氏などによる案内で、天理教教会本部の神殿を参拝しました。
天理図書館、天理参考館を取材したルポエッセイは、2025年の秋頃、月刊「なごみ」にて掲載される予定です。