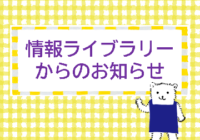天理大学創作ダンス部は、12月22日、なら100年会館大ホールにて、「一般社団法人青少年育成アスリートプロジェクト創作ダンス公演2024 創部55周年 第20回単独公演 Beyond―この瞬間を駆けぬける―」と題した単独公演を開催しました。
創部55周年を記念した今回の公演は、オーストラリアのメルボルンに拠点を置き活躍するアーティスト、ゆみ・うみうまれ氏が特別作品の振付演出を担当する関係から、オーストラリア政府の助成を得るとともに、スポーツ全般の普及と日本の未来を支える若者たちの人材育成を目的とした「一般社団法人青少年育成アスリートプロジェクト2024」が趣旨に賛同する意向から共催公演となりました。
特別作品「あめつちの聲(こえ)~in the middle of the awe」で幕を開けました。この作品はゆみ・うみうまれ氏が、「陰陽五行思想」からインスピレーションを得て創作、振付演出したもの。冒頭を飾ったこの特別作品には、ゆみ・うみうまれ氏の実弟であり、世界中で活躍している水墨画家 土屋秋恆氏による墨絵の映像が演出として組み込まれました。
また作品のイメージから本学の雅楽部に共演を依頼し、舞台での共演が実現。さまざまなつながりが生み出したこの特別作品は、記念公演に相応しい作品として上演され、万雷の拍手を浴びました。




本公演では、「第12回全国高等学校ダンス部選手権 DANCE CLUB CHAMPIONSHIP」で準優勝の樟蔭高等学校ダンスクラブや、「第36回全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)」で「日本女子体育連盟会長賞」を受賞した帝塚山学院高等学校ダンス部の賛助出演作品も披露されました。また、芦屋学園高等学校、神戸野田高等学校の高校生も、「尖った風」にダンサーとして出演いただきました。
また本学卒業生である茉莉花氏の振付、KiiM 3名の作舞よる「おかえり~映画「すずめの戸締まり」より~あの日、みんなが言えなかった声を聴く」(「Anime Choreography Legend」アート賞受賞作品)など、本学卒業生の作品や現役学生とのコラボ作品なども披露されました。


公演のラストで披露されたのは、本学創作ダンス部が「第36回全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)」において「日本女子体育連盟会長賞」を受賞した「Beyond-イブン・バットゥータの見据えたこの世界(ほし)の未来-」。
この作品は、学生たちが、まだ簡単には人が行き交うことができない約700年前に旅をすることに思いをはせて創作したもので、プロローグでは、時の流れのなかで異なる民族、宗教、文化、言語など様々な価値感が生まれたことを表現しました。
また、イブン・バットゥータが未知との出会いを求めて、何万里もの平原を馬と駆け抜けた様子をダイナミック且つしなやかなダンスで表現し来場者を魅了しました。
クライマックスのシーンでは、バットゥータが他者の心を知り価値を認め、開かれた心で対話する喜びと感動を生き生きとした生命力あふれた演技で表現し、来場者は渾身のステージに引き込まれました。


エンディングでは、創作ダンス部部員をはじめ、顧問である体育学部塚本順子教授や卒業生、本学雅楽部部員など、この日の出場者全員がステージに上がり、来場者へお礼の意味を込めたダンスを披露。拍手喝采のなか、出演者がアンコールの声に応えて最後の踊りを披露し創部55周年の単独公演の幕を閉じました。



川村ひなた主将(体育学科4年・樟蔭)コメント

今年一年、公演テーマ「Beyond―この瞬間を駆けぬける―」のように、心と心がつなが り合えるようなチームと作品づくりを目指して部員 22 名とともに駆けぬけてきました。最後に披露しました作品は、私たちの未来もいろんな人とつながりあい、感動と喜びがあふれていると信じて何度も皆で創作を重ね、本日ご来場の皆さまにご鑑賞いただくことで完成いたしました。今日のこの日を全員で迎えられたのは、どんな時でも支えてくださった塚本先生をはじめ、いつもあたたかく応援してくださる OB や OG の方々、家族や友達、そして日々の活動のなかでいくつもの壁を乗り越えあった大好きな後輩たちと同期のおかげです。本当にありがとうございました。
体育学科教授・塚本順子創作ダンス部部長コメント
本公演にご出演いただきました、ゆみ・うみうまれ氏・土屋秋恆氏、快くお力添えいただきました佐藤浩司先生と雅楽部の皆さま、強力なお力添えで支えていただきました一般社団法人青少年育成アスリート様とオーストラリア政府、温かく学生の課外活動を常に支えて頂いております天理大学や地域の皆さまに心から感謝申し上げます。不断の努力で身体と向き合い、つくり・おどり・みる、身体表現・ダンスは、人と人をつなぐからだを讀み、感じる身体的なコミュニケーションに根差すものです。アートとしての身体表現・ダンスによって言葉と共に共有するイメージの世界は、自己と他者を認め合う、多様性へとつながります。学生たちにとってのそうした学びの活動として、本公演にご来場くださった観客の皆様も、欠くことのできない存在です。すべての皆さまに心から、感謝申し上げます。ありがとうございました。