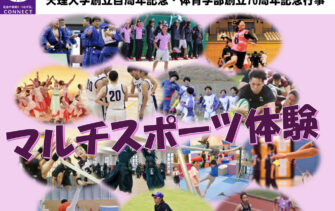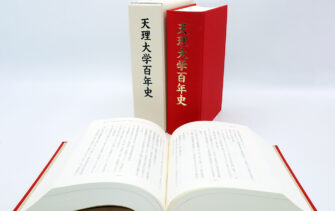ニュース
記事を絞り込む
-

2025.07.04 人文学部国際学部体育学部医療学部社会連携6つのCONNECT地域社会とつながる学部学科とつながる
地域とともに学びを深める ― 天理大学2025年度公開講座の取り組み
天理大学では、2025年度の公開講座を4月から12月にかけて随時開催しています。そのなか、大阪市立阿倍野市民学習センターとの共催による...
-

2025.07.04 社会連携地域・企業との連携地域社会とつながる
第4回てんだいフェスタ開催 コーヒーバトルで天理大学が優勝飾る
6月8日(日)、天理駅前広場コフフンで開催された「第4回てんだいフェスタ」において、関西の8大学が参加したコーヒーバトルが実施され、...
# てんだいフェスタ
-

2025.07.04 クラブ・サークル社会連携地域・企業との連携6つのCONNECT地域社会とつながる
馬の餌やり体験を行いました。
6月30日、天理大学はJRA日本中央競馬会がすすめる学校招待事業の一環として、天理市立朝和幼稚園の年長組を対象に「馬の餌やり体験」を西...
# ホースセラピー
-

2025.07.04 社会連携生涯学習公開講座記録
《公開講座記録》【人文学へのいざない】第4回 「社会福祉とボランティア活動」
《公開講座記録》【人文学へのいざない】第4回 ●2025年6月14日(土) 午後1:30●テーマ:「社会福祉とボランティア活動」●講師...
# 公開講座
-

2025.07.04 医療学部看護学科教育・研究6つのCONNECT地域社会とつながる
【授業紹介:地域健康教育方法論】(看護学科2年生)②
この授業では、地域に暮らす人々の健康ニーズをとらえ、地域の特性を踏まえた健康教育ができることを目指しています。 今年度は、天理市に加え...
# 授業紹介
-

2025.07.04 体育学部体育学科社会連携地域・企業との連携企業・一般の方へ6つのCONNECT地域社会とつながる
天理大学創立百周年記念 地域の子どもに向けたスポーツ体験「マルチスポーツ体験」(8/3・8/9開催)
多様なスポーツに出会って、好きなスポーツを見つける!スポーツに親しむ、スポーツを続けるにコネクト! 天理大学創立百周年記念・体育学部創...
-

2025.07.04 医療学部看護学科社会連携地域・企業との連携在学生の方へ在学生保護者の方へ企業・一般の方へ6つのCONNECT地域社会とつながる
天理大学医療学部看護学科主催「市民健康講座」(7/29〜8/1開催)
看護学科では、2年次生対象の「地域健康教育実習」の一環として、次のとおり健康講座を開催します。どなたでも自由に参加できますので、直接に...
-
2025.07.02 その他
本学学生の不祥事に関するご報告と対応について
このたび、本学ラグビー部員が違法薬物である大麻を所持していたこと等が判明し、関係者の皆様、地域の皆様、そして本学に関心を寄せてくださる...
-

2025.07.02 在学生の方へ在学生保護者の方へ6つのCONNECTその他
『天理大学百年史』が刊行されました
天理大学創立100周年を記念して、『天理大学百年史』が刊行されました。 編集:天理大学百年史編纂委員会発行:天理大学装丁:A5判 14...