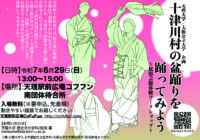今年度、新カリキュラムとして始まった民俗学コース科目の「フィールドワークからみる民俗文化」では、普段の教室での講義にくわえて、実際にフィールドに出て見て学ぶ活動も行っています。新年度が始まったばかりの5月初旬、世間はゴールデンウィーク中ではありましたが、受講生とともに天理市内で行われる野神行事の見学に行ってきました。野神行事は5月から6月にかけて、奈良盆地一帯で行われる農耕の行事です。今回は、天理市新泉町(5月3日、国選択無形民俗文化財)および天理市平等坊町(5月5日)の野神行事を見学しました。
今回、見学に参加したのは歴史文化学科の2年次生(9名)と、現在国際学部日本学科に台湾からの交換留学生として在籍している学生(4名)です。ほとんどの学生にとっては、民俗行事を見学すること自体が初めてでしたので、貴重な経験になったのではないでしょうか。事前に資料を読んで祭りの概要を理解して見学に臨みましたが、実際に見学してみると資料との違いや、新たな課題(祭りを継承していくこと、等)を感じた学生も多かったようです。
このように歴史文化学科の学びのフィールドは大学の外にも広がっています。今後も、教室で学んだ知識をもとに、フィールドへ出て五感で考える授業を継続していきたいと考えています。
(歴史文化学科民俗学コース教員 松岡 薫)


参加学生の声
古くから行われているお祭りということで、「ジャジャウマ」など古くから伝承されている文化を見るのは初めての経験でした。また、地元の子どもたちと一緒に学生代表として祭りに参加させていただけたのもとても嬉しかったです。 (歴史文化学科民俗学コース2回生 西尾真和)
私の地元では野神祭りのようなお祭りをしていないので、とても斬新で、いい経験になりました。同じ野神祭りでも子供は減っているけれど神聖な行事として伝統的なやり方をしている新泉町と、人は多いけれど子供のイベントとして儀礼感の薄い平等坊町という、2つの地区の違いを知ることのできたよい機会になりました。やはり民俗行事の存続は難しそうだなと感じました。 (歴史文化学科民俗学コース2回生 佐々木未来)
今日は、天理市新泉町の野神祭を参加しました。お祭りの儀式を拝見したり、地元の方の話を聞いたり、かなり充実な時間を過ごしました。時代が変わっても、変わってないのは神様への敬意と、こういう歴史悠久な文化を維持できるために精一杯頑張ってる人たちの心です。外国人の私にとっては、かなり貴重な経験になりました。 (国際学部日本学科 李沛沂)