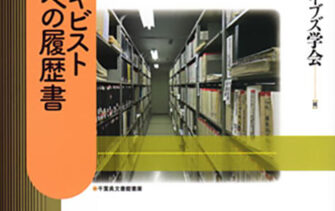ニュース
記事を絞り込む
-

2025.11.18 医療学部看護学科教育・研究社会連携受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ
【授業紹介】災害看護論 メディカルラリー
4年生の必須科目である災害看護論で、看護学生メディカルラリーを実施しました。1日を通して、被災者役、看護師実践者役となりました。実践者...
# 臨床判断# 看護学科# 授業紹介
-

2025.11.18 社会連携生涯学習公開講座記録
《公開講座記録》【「大和学」への招待 -橿原市の歴史と文化-】第2回 奥野陣七を知っていますか?
《公開講座記録》【「大和学」への招待 -橿原市の歴史と文化-】第2回 ●2025年10月18日(土) 午後2:00●テーマ:「奥野陣七...
# 公開講座
-

2025.11.17 総合教育センター教職員の新刊案内人文学部
古賀 崇 教授 共著書(分担執筆)『アーキビスト 未来への履歴書』が出版されます。
日本アーカイブズ学会/編、岩田書院、2025年11月刊行、定価:1600円 (税別) 本書は、日本アーカイブズ学会の創立20周年を記念...
-

2025.11.17 社会連携生涯学習
TV放送のお知らせ【ホースセラピー活動】
11月14日(金)、NHK奈良放送局の「ならナビ」(午後6:30〜午後7:00)のコーナー「ならコレ!」において、天理大学のホースセラ...
# ホースセラピー
-

2025.11.17 人文学部心理学科大学院臨床人間学研究科臨床心理学専攻
大学院進学説明会を開催しました
11/11(火)に3年生向け大学院進学説明会を開催しました。会では、大学院進学希望者を対象に、臨床心理学系の大学院ではどのような勉強を...
-

2025.11.17 医療学部看護学科受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ地域社会とつながる
【教員コラムNo,27】
相手の声をしっかり聴けているかわたしたち看護師の役割のひとつに患者の声をしっかりと聴くということがある。もちろん、乳児や認知機能の低下した方など言葉を話すことが難し...
# 看護学科# 教員コラム
-

2025.11.14 人文学部歴史文化学科受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ
「山の辺の道を歩く2025」を開催
11月8日、歴史文化学科主催による恒例の課外活動「山の辺の道を歩く2025」が開催され、歴史文化学科の学生・教員、計27名が参加しまし...
# 山の辺の道# 考古学コース# 民俗学コース
-
2025.11.14 受験生の方へ
合格発表について【日本学科留学生<国外在住>選抜】
「日本学科留学生<国外在住>選抜」の合格発表は、2025年11月21日(金)12:00より掲載致します。...
-

2025.11.13 国際学部国際体験受験生の方へ在学生の方へ在学生保護者の方へ受験生の保護者・高校教職員の方へ6つのCONNECT世界とつながる学生同士がつながる学部学科とつながる
天理大学創立百周年記念行事
国際学部主催「留学プレゼンテーション大会」を開催天理大学は11月1日、創立百周年記念行事の一環として、国際学部主催「留学プレゼンテーション大会『世界と、日本と「つながる」わたし』」を...