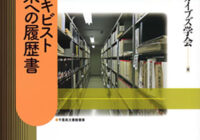《公開講座記録》【「大和学」への招待 -橿原市の歴史と文化-】第2回
●2025年10月18日(土) 午後2:00
●テーマ:「奥野陣七を知っていますか?」
●講師 幡鎌 一弘 (歴史文化学科 教授)
内容
奈良県で橿原神宮を知らない人はいないが、その創建期に神武天皇陵や橿原神宮の整備活動などに深く関わった奥野陣七を知る人は、おそらくほとんどいないだろう。
自伝によれば、奥野陣七(1842〜1926)は楢原村(現・御所市)に生まれた。天誅組に協力し、中山忠光や三条実美とつながった。慶応3年には鷲尾隆聚の高野山挙兵に加わり、明治初年には横井小楠・大村益次郎暗殺、外山・愛宕両卿のクーデターへの嫌疑を受けた。
1870年代後半からは古蹟調査をはじめ、畝傍に転居した。1886年には『皇朝歴代史』、翌年には「皇祖天神歴代皇霊遥拝之巻」「伊勢神宮官国幣社遥拝之巻」を刊行し、天皇家への崇敬の普及に努めた。
1889年には大成教畝傍橿原教会の設立を主導し、認可を受ける。同教会は神武天皇の御霊を奉崇し、御陵参拝を奨励した。設立願には、県会議員や戸長クラスの奈良県の名士に加え、大阪・京都・東京の人士も賛同者として名を連ねた。こうした人脈は、1898年に「橿原十六景」を選定し、絵や書を集めたときにも、いかんなく発揮されている。
1890年に橿原神宮が創建されると、奥野は神宮の神威宣揚に協力した。しかし、その活動は神宮の活動と紛らわしく、奥野の教会が活発になればなるほど、橿原神宮の実利を損ないかねなかった。また、同業者である新海梅麿との軋轢も深まっていった。とはいえ、奥野の活動は橿原神宮にとっても必要であり、神社と協力しながら活動を続けていた。
しかし、西内成郷が宮司になると奥野との対立が表面化し、西内の訴えにより、奥野の畝傍橿原教会は公認を取り消され、神社の祭典会幹事も免職された。西内は橿原神宮直轄の敬神講(のち橿原神宮講社)を設立し、人々の信心を直接掌握しようとしたのである。
公的な立場を失った奥野は、『富貴長寿の枝折』(1909年)、『大和国の歌』(同年)、『家庭の教歌』(1910年)を刊行し、神武天皇崇敬とあわせて生活改善・健康増進、とりわけ通俗道徳の普及を掲げて活動した。
奥野の活動の背景には、奈良県下で活発化していた教派神道の潮流がある。新海梅麿の神道畝火教会、防南忠次郎の神習教畝火教会、松本善録の大成教畝傍太祖教会などが並立した。実際の活動目的は神武天皇の宣揚で共通していたにもかかわらず、それぞれが独自性を主張できたのは、神道の各派が独自の組織たり得た一方で、内部的に教義的統一性が低かったことによるものである。
さらに、神武陵は明治初年から信仰・観光の対象となり、宗教的信仰と経済的事業が交錯する場となったことも注意すべきである。江戸時代には、寺社・宿の連携による巡礼や社寺参拝が行われていた。このことは、奥野が『歴代御陵墓参拝道順路御宮趾官国幣社便覧』を刊行して陵墓と官国幣社巡拝の手引きを提供したことにもつながった。
奥野陣七の軌跡は、神武陵や橿原神宮の整備過程において、官と民(国家主導とは異なる民間の信仰運動)が果たした役割を示している。同時に、教派神道の多様性と内部対立、神宮と教会の力学、信仰と観光・出版事業の結合など、近代日本宗教史の複雑な構図を読み解くための重要な手がかりともなっているといってよいだろう。