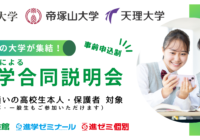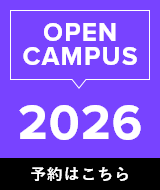10月25日、おやさと研究所では、公開教学講座シリーズ「『元の理』の学術的研究とその新しい展開を求めて」の第7回目を開催しました。今回は、島田勝巳研究員(宗教学科教授、本学副学長)が「『元の理』と天理教学」という演題で講演いたしました。島田研究員は、宗教学・天理教学が専門分野です。宗教学に関しては主に西洋キリスト教思想史を研究しています。
天理教の教祖は、「元初まりの話」を端的に真実の話として語られました。しかし、「元の理」を学術的に研究するとなると、宗教的真理と歴史的・科学的事実の二分法が前提となり、一種の「二重真理説」のディレンマに陥るのではないか、と島田研究員は問題提起を行いました。
島田研究員は、従来の天理教学がこのディレンマを「元の理」の真理性をめぐる問いの中で捉えてこなかったことも指摘。その理由として、天理教学は近代キリスト教神学が経験した歴史研究や近代科学との対峙(思想史的イニシエーション)を経験せずに誕生したことがあったことを述べました。
天理教学の持つそのような歴史的特殊性の一端は、諸井慶徳「天理教神学序章」の記述中に見出されます。そこでは、他の一神教的伝統の神学に伍する天理教(神)学の権利主張に加え、自らの普遍的な真理性の主張が“特殊”だという自覚と、その“普遍化”への取り組み(弁証)の姿勢の共存があるとされます。
その上で、島田研究員は、「元初まりの話」の真理性を、教祖の姿勢において、また「おふでさき」の中の言及に即して論じました。前者では、大和神社での神祇問答の中でこれが主張されます。後者では、高山の説教・学問に対する「神のはなし」の持つ真理性と共に、人間が努力して「もとはじまり」の根を掘ることが強調されます。
最後に島田研究員は、たとえ「元の理」が荒唐無稽に見えても、それに人々が賭けようとする根源がこの教えの中にあるとする河合隼雄の言葉を紹介し、「元の理」について思案しつつ、「元の理」と/を“生きる”こと、そしてこれを“教学的に”意義づけることも可能ではないかと示唆しました。
講演後、フロアとの間で活発な質疑応答や意見交換が行われました。
この公開教学講座シリーズは毎月25日に開催されます。事前申し込みは不要です。
次回、第8回目の公開教学講座は、11月25日(火曜)13時より、天理大学研究棟3階の第1会議室にて開催されます。岡田正彦研究員(宗教学科教授)が「『元の理』とこふき」と題して講演いたします
(おやさと研究所・金子昭)