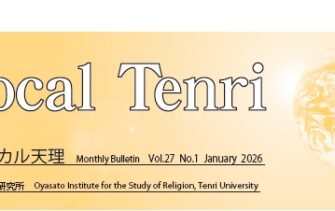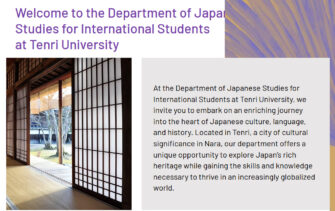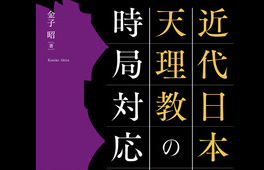ニュース
記事を絞り込む
-

2026.01.21 関連施設附属おやさと研究所刊行物Glocal Tenri
『グローカル天理』2026年発行分(通巻313号ー)
2026年『グローカル天理』第2号(通巻314号)を発行 2026年『グローカル天理』第1号(通巻313号)を発行...
-
2026.01.21 受験生の方へ入試情報
一般選抜(前期)志願者速報(確定)
志願者速報は、入学検定料の納入が確認された志願者数を集計して、公表しています。なお、志願者数の確定は出願締切日から数日後となり、「志願...
-

2026.01.20 学長室CONNECT国際学部英米語学科国際体験交流協定校世界とつながる
アメリカ・ハイラインカレッジとの協定校締結
2025年11月17日(月)、永尾学長はアメリカ・ハイラインカレッジを訪問し、同校と学術交流協定を締結しました。これにより、ハイライン...
-
2026.01.20 受験生の方へ入試情報受験生の保護者・高校教職員の方へ
1月29日(木)・1月30日(金)実施の入学者選抜について
受験される皆さまへ 実施する選抜は以下の通りです。 1月29日(木) 総合型選抜 一般選抜 総合型選抜(特別) 1月30日(金) 一般...
-

2026.01.19 学生生活社会連携地域・企業との連携天理市行政施策貢献学生認定制度世界とつながる地域社会とつながる学生同士がつながるビジネスとつながる
令和7年度後期「天理市行政施策貢献学生認定式」が行われました
1月16日、天理市役所において令和7年度後期「天理市行政施策貢献学生認定式」が執り行われ、天理市の行政施策に貢献した学生19名に対し、...
-

2026.01.19 国際学部外国語学科社会連携地域・企業との連携6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながるビジネスとつながる
外国語学科インドネシア語コースが「在大阪インドネシア共和国総領事館インドネシア貿易振興センター」を訪問
2025年12月3日、天理大学外国語学科インドネシア語コースの学生が、「在大阪インドネシア共和国総領事館 インドネシア貿易振興センター...
# インドネシア語コース
-

2026.01.19 国際学部日本学科(留学生対象)
日本学科(留学生対象)英語ホームページ開設
世界各地にいるみなさんに知ってもらうために、日本学科(留学生対象)では英語のホームページを開設しました。 英語のホームページはこちら。...
-

2026.01.15 教職員の新刊案内教育・研究附属おやさと研究所その他出版物
金子昭おやさと研究所教授著『近代日本国家と天理教の時局対応』が出版されました。
法蔵館・2025年12月刊・全320頁・本体6,000円+税 本書は、令和7年度天理大学学術図書出版助成の交付を受けて出版されました。...
-

2026.01.15 国際学部外国語学科6つのCONNECT世界とつながる地域社会とつながる学生同士がつながる
天理大学創立百周年行事 国際学部市民講座「世界のことばとぶんか」
第12回「ロシア語-多様な文化への扉-」を開催しました天理大学では、創立百周年記念事業の一環として、国際学部による市民講座「世界のことばとぶんか」(全12回)を2025年4月より開催してき...
# 「世界のことばとぶんか」# ロシア語コース