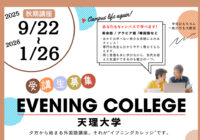本年、創立百周年を迎えた天理大学では、その記念行事の一つとして、国際学部による市民講座「世界のことばとぶんか」(全12回)を、4月より順次開催しています。
この講座では、天理大学で学べる10言語(韓国・朝鮮語、中国語、英語、タイ語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語、ブラジルポルトガル語)をはじめ、「世界のなかの日本」や「日本のなかの多文化」といったテーマを、体験授業や講義を通じて紹介しています。講師は国際学部の教員が務め、在学生や留学生もスタッフとして参加しています。
8月23日には、第6回講座「日本における多文化共生と介護ケア人材」が開催されました。近年、日本では外国人労働者の受け入れが進み、多文化共生社会への歩みが本格化しています。今回の講座では、「日本で働くこと」「日本で働いてもらうこと」の意味について、参加者とともに考える機会にしたいと、本学国際文化学科教員が企画しました。
国際文化学科では、「多文化共生社会の実現を支える」人材の養成を目指し、地域で暮らす外国人とのコミュニケーション手段として「やさしい日本語」を授業科目に取り入れるなど、実践的な教育を行っています。

イベントでは、まず、本学国際文化学科の山田政信教授が「日本で働くこと、日本で働いてもらうこと」をテーマにミニレクチャーを実施。外国人労働者の現状や課題について具体的な事例を交えながら解説し、外国人が日本で働き暮らすことの大変さに思いを馳せながら、互いに協働することの大切さを伝えました。
続いて、奈良東病院グループ(医療法人健和会/社会福祉法人大和清寿会)より、鉄村信治理事長と村島伸子事務課長をお招きし、「奈良東病院グループの概要紹介」と題して講演をいただきました。介護・医療現場における外国人スタッフの活躍をはじめ、受け入れ体制の工夫などが紹介されました。


最後に、現在同病院グループ傘下の語学学校や福祉施設で勤務されている外国出身の方2名による「体験談」が発表されました。
本学日本語専攻(現・日本学科)の卒業生であるレ ヴァン タイ氏は、ベトナムから天理大学へ留学した経緯や在学中の学びを紹介し、現在は「HAYAMA International Language School」で職員として活躍していることを語りました。また、「天理大学百周年という記念すべき節目に、こうしたイベントで講演できてとても嬉しい」との言葉も述べました。
「特別養護老人ホーム 清寿苑」で介護福祉士として働いているウルファ トゥン ニマ氏は、日々の仕事内容を交えながら、日本で働くことへの思いを語り、参加者の共感を呼びました。



今回のイベントでは、市内に店舗を構える「バインミーはなちゃん」によるベトナム発祥のサンドイッチ「バインミー」の試食も行われ、参加者の関心を集めました。会場には店舗スタッフのティエウ ミン チャンさんも来場され、「バインミー」についての説明も行われました。
さらに、奈良県内で働くベトナム人の方々や、在日韓国人で介護支援専門員として活躍されている方など、多様な人々が産学共同に加わり、共にイベントを作り上げました。ひとときとはいえ、会場には「多文化共生」の花が咲いたようでした。

国際学部市民講座「世界のことばとぶんか」は、2026年1月まで毎月開催予定です。会場周辺では、対象言語圏の音楽や文化紹介、世界各国の「遊び」が体験できるコーナーも設置予定です。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
国際学部市民講座「世界のことばとぶんか」の予定(詳細は大学HPでご案内します)
- 第1回:4月26日(土)韓国・朝鮮のことばとぶんか
- 第2回:5月17日(土)台湾茶の世界 香りと味わいの旅
- 第3回:6月21日(土)スペイン語圏まるかじり! 食文化と紙ひこうきの旅
- 第4回:6月28日(土)英語で「つながる」世界
- 第5回:7月12日(土)フランス語
- 第6回:8月23日(土)日本のなかの多文化
- 第7回:9月20日(土)ドイツ語
- 第8回:10月11日(土)マンガでつながる世界と日本
- 第9回:10月25日(土)タイ語
- 第10回:11月22日(土)ブラジルポルトガル語
- 第11回:12月 6日(土)インドネシア語
- 第12回:1月10日(土)ロシア語
会場:天理駅サテライトキャンパス(天理駅前広場南団体待合所)
お問合せ:kouhou※sta.tenri-u.ac.jp(※は@に置換してください)