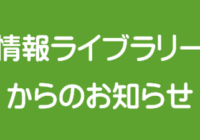7月5日、天理大学を会場に、天理台湾学会(会長=山本和行・国際学部教授)が第34回研究大会を開催しました。台湾からの参加者を含め、研究者や学生ら50名近くが参加しました。
天理台湾学会は、1991年、天理台湾研究会の名称で発足し、天理大学に事務局を置く国際的な学会です。例年、天理大学を会場に研究大会を開いています。
今回、研究発表の部では、6名の研究者(全員台湾から参加)が発表しました。
午前の部では、「戒厳時期秦爐「軍用燃油の密売」事件に関する論考」(陳依婷・国立成功大学大学院生)、「日本統治期における乙未戦争を題材とした小説の研究―『大和武士』(1896年)と『台湾縦貫鉄道』(1944年)を中心に」(鍾志正・国立中央大学大学院生)、「台湾における特殊言語景観―“諧音梗”を中心に」(陳順益・中国文化大学副教授)の3つの発表が行われました。
午後の部では、まず特別企画として、ミニシンポ「戦前・戦後の台湾の政治体制と天理教の伝道の歴史的歩み―『天理教台湾伝道史』刊行に寄せて」が行われました。発表は「日本統治時代の天理教台湾伝道」、「中華民国時代の天理教台湾伝道」について、それぞれ『天理教台湾伝道史』(2025年3月刊行)の編集委員を務めた高佳芳・金子昭の2名が担当いたしました(当初予定していた発表者と一部変更があります)。
その後、「『第二の故郷』を振り返る―大河原光廣の台湾に関する作品を論じる」(蕭亦翔・国立清華大学大学院生)、「日本統治期の俳人・阿川燕城の台湾季節観」(沈美雪・中国文化大学教授)、「冷戦期における呉濁流文学のアメリカでの流通と受容」(王恵珍・国立清華大学教授)の3つの発表が行われました。
最後に、川瀬健一・東洋思想研究所主幹が「台湾映画研究35年」と題して記念講演を行いました。川瀬氏は自らのライフヒストリーを交えながら、戦後台湾の著名な映画監督や文学者との交流について熱く語られ、会場を魅了いたしました。
なお、同学会からは当日付で研究誌『天理臺灣学報』第34号が刊行されました。
(おやさと研究所教授 金子 昭)