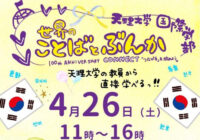ここ最近「心理的安全性(psychological safety)」という言葉を耳にする機会が何度かあり、以前から「読もう、読もう」と思って先延ばしにしていたエイミー・C・エドモンドソン(著) 「恐れのない組織―「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす」をようやく開きました。
「心理的安全性(psychological safety)」とは、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・C・エドモンドソン教授が1999年に提唱した概念で、「不安や恐れを感じることなく安心して発言や質問が出来る環境や関係性」のことを指します。
職場において心理的安全性が高まると、風通しがよくなり人間関係の改善が期待できるうえ、仕事に集中できる環境が整うといわれています。さらにはストレスが減るなどの効果も期待できるといわれています。近頃では、一般企業や医療現場の心理的安全性にとどまらず、看護教育現場における心理的安全性についても議論されていて、そこでは「学生が学習環境に安心できなければ十分な学習は期待できない」といわれています。学内での演習や臨地実習ではじめてのことに緊張しながら一生懸命に取り組もうとする学生の姿をみると、あらためて心理的安全性の高い学習環境の提供が重要だと感じます。
いよいよ新年度が始まります。
新しい仲間とはじめて看護を学ぶ1年生
年度末には患者さんを受け持つ実習がある2年生
秋学期からは長期にわたる臨地実習を控えた3年生
国家試験の受験を意識しはじめる4年生
それぞれが楽しみな気持ちを持ちながらも漠然とした不安を抱えていることだと思います。
学生が安心できる学習環境づくりを考える1年にしていきたいと思います。
執筆者(医療学部・看護学科 森嶋道子・准教授)